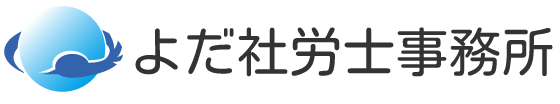発達障害と障害年金(1)
1. 発達障害についての理解
発達障害については、国立精神・神経医療研究センター(NCNP)が運営している「こころの情報サイト」で以下のように記載されています。
発達障害は、脳の働き方の違いにより、物事のとらえ方や行動のパターンに違いがあり、そのために日常生活に支障のある状態です。発達障害には、知的能力障害(知的障害)、自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症(ADHD)、限局性学習症(学習障害)、協調運動症、チック症、吃音などが含まれます。同じ障害名でも特性の現れ方が違ったり、他の発達障害や精神疾患を併せ持つこともあります。
発達障害には大きく分けて「自閉症スペクトラム(ASD)」、「注意欠陥・多動性障害(ADHD)」、「学習障害(LD)」があり、互いに重複したり、自閉症スペクトラムや注意欠陥・多動性障害に知的障害が関わってくることもあります。それぞれの特徴と支援のポイントをまとめると下表のようになります。
| 分類 | 正式名称 | 主な特徴 | 得意・苦手の傾向 | 支援のポイント |
|---|---|---|---|---|
| ASD | 自閉スペクトラム症 (Autism Spectrum Disorder) |
・コミュニケーションや対人関係の難しさ ・興味や行動のこだわり ・感覚過敏/鈍麻(音・光・触覚など) |
・得意分野に強い集中力を発揮 ・パターン認識やルールに基づいた作業が得意 ・柔軟な対応や曖昧な指示が苦手 |
・指示は具体的に、視覚的に伝える ・環境を整え、見通しを持たせる ・得意分野を活かした役割分担 |
| ADHD | 注意欠如・多動症 (Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder) |
・不注意(ケアレスミス・忘れ物) ・多動(じっとしていられない) ・衝動性(思ったことをすぐ行動に移す) |
・興味あることに強い集中力(ハイパーフォーカス) ・アイデア発想が豊富 ・ルーチンや事務作業が苦手 |
・環境調整(音・視覚刺激を減らす) ・スケジュールやToDoの視覚化 ・ポジティブフィードバックで行動を強化 |
| LD | 学習障害 (Learning Disability) |
・知的発達に遅れはないが「読む・書く・計算」の特定分野が苦手 ・読字障害(ディスレクシア)、書字障害(ディスグラフィア)、算数障害(ディスカリキュリア) |
・得意分野は平均以上に発揮可能 ・視覚・聴覚からの学習スタイルに偏り ・苦手分野の成績や業務評価で誤解を受けやすい |
・ICTツール(読み上げソフト、ワープロ、計算補助ツール)の活用 ・合理的配慮(時間延長など) ・得意な方法で力を発揮できる環境づくり |
2. 障害認定基準:E 発達障害
(1)発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものをいう。
(2)発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により、対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行う。
また、発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
(3)発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。
(4)各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
1級:社会性やコミュニケーション能力が欠如し、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とする。
2級:社会性やコミュニケーション能力が乏しく、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要。
3級:社会性やコミュニケーション能力が不十分で、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受ける。
(5)日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。
(6)就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。したがって、就労していることをもって直ちに日常生活能力が向上したと捉えず、療養状況や仕事内容、職場での援助内容、同僚との意思疎通などを十分に確認したうえで判断すること。
3. 発達障害・知的障害と精神疾患の併発時の取り扱い
原則:併合(加重)認定はしない
障害認定基準では、
発達障害 × 他の精神疾患、
知的障害 × 他の精神疾患の場合、
「併合認定(加重認定)」は行わないと明記されています。
つまり「知的障害〇級+うつ病〇級=合算してより重い等級」にはならず、総合的に判断して一つの等級が決まる仕組みです。
疑義照会「給付企 No.2011-1」:知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合の取扱いについて
この通知は、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第8節 精神の障害」において、知的障害/発達障害と他の精神疾患が併存する場合の扱いについて、事務上不明な点を整理するための疑義照会に対する日本年金機構本部の回答を周知するものです。
回答内容(主な取扱い)
(1) うつ病又は統合失調症と診断されていた者に後から発達障害が判明するケース → 診断名の変更に過ぎないことが多く、新たな疾病ではないため「同一疾病」と扱う。
(2) 発達障害と診断された者に後からうつ病や神経症で精神病様態を併発 → 発達障害が起因して発症したと考えられるため「同一疾病」と扱う。
(3) 知的障害と診断された者に後から発達障害が診断 → 原則「同一疾病」。ただし軽度の知的障害で20歳以降に初めて発達障害として受診した場合は「別疾病」。
(4) 知的障害に後からうつ病が発症 → 知的障害が起因して発症したと考えられるため「同一疾病」。
(5) 知的障害に後から神経症で精神病様態を併発 → 「別疾病」。ただし統合失調症(F2)の病態を示す場合は統合失調症併発、気分障害(F3)の場合はうつ病併発として扱う。
(6) 発達障害や知的障害に後から統合失調症が発症 → 原則「別疾病」。ただし稀に発達障害や知的障害の症状の一部として統合失調症様態を呈する場合があり、その場合は「同一疾病」と扱う。
表で整理
| ケース | 取扱い | 補足説明 |
|---|---|---|
| ① うつ病/統合失調症と診断されていた者に、後から発達障害が判明 | 同一疾病 | 多くは診断名の変更に過ぎず、新たな発症ではないため |
| ② 発達障害に、後からうつ病や神経症で精神病様態を併発 | 同一疾病 | 発達障害が起因して二次的に発症する場合が一般的 |
| ③ 知的障害と診断されていた者に、後から発達障害が診断された | 原則:同一疾病 ただし軽度知的障害で20歳以降に初めて発達障害で受診した場合は別疾病 |
原則は同一疾病。ただし軽度知的障害で20歳以降に初めて発達障害で受診した場合は別扱い |
| ④ 知的障害に、後からうつ病が発症 | 同一疾病 | 知的障害が起因して発症したと考えるのが一般的 |
| ⑤ 知的障害に、後から神経症で精神病様態を併発 | 別疾病 | ただし統合失調症(F2)の病態なら統合失調症併発、気分障害(F3)ならうつ病併発として扱う |
| ⑥ 発達障害・知的障害に、後から統合失調症が発症 | 原則:別疾病 | 統合失調症は独立した疾病。ただし稀に発達障害や知的障害の症状として統合失調症様態を呈する場合は同一疾病 |
4. まとめ
(1) 発達障害で生きづらさを抱えておられる方は多い。
生きづらさ、不適応行動、対人関係や意思疎通の困難さ、就労(職場不適応)といった切り口から考えることが必要。
⇒ 認定基準やガイドライン等に当てはめ、社会行動やコミュニケーション能力、不適応な行動の度合いがどの程度かを考える。
(2) 発達障害の初診日は、知的障害を伴うか伴わないかで取り扱いが異なる。
(3) 神経症の症状が発達障害に起因している場合がある。
(4) 社会的治癒については、社会的治癒の法理だけでなく、医師への丁寧な説明や理解も踏まえ、それを医証に反映できるか検討することが必要。
CONTACTお問い合わせ
-
よだ社労士事務所は、
障がい者雇用支援、IT活用支援、年金制度に関するご相談など、
企業と個人の幅広い課題をサポートしています。 -
ご相談は無料です。 もし今、お悩みを抱えているなら、まずは一度お問い合わせください。メールでも、お電話でもOKです。無理な勧誘や押しつけは一切いたしませんので、ご安心ください。
企業の皆様へ、「障がい者雇用をどう進めればいいかわからない」「社内のDX化を進めたい」「社員のスキルアップを支援したい」そんなお悩みがあれば、ぜひご相談ください。
雇用の課題からDXサポート、人材育成・教育支援まで、貴社に最適な解決策をご提案します。
小さな疑問でも構いません。一歩を踏み出すことで、新しい可能性が開けます。
お気軽にご相談ください。